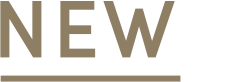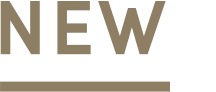2018.031
灯りを点けて桃の花を添えましょう
暦ではもう春は来ていますが、毎日寒い日は続き、本当の春はまだまだのようですね。
そんな中、3月になりました!
最初の土曜日にはひな祭りがあります!女の子にとっては特別な日ですね。
東急ステイ用賀でもひな祭りをお祝いしたい!
という事で、第3回はちらし寿司を作ってみたいと思います!
第3回
『簡単かわいいコップちらし寿司』
材料 (2人前)
パックご飯 2パック
寿司の素 2パック
たまご 2個
砂糖 大さじ1
みりん 大さじ1
しょうゆ 小さじ1/2
塩 少々
豚ひき肉 200g
みりん 大さじ2
砂糖 大さじ2
しょうゆ 大さじ2
かにかま 5本
絹さや 20枚
プチトマト 2個
作り方
1 パックご飯を電子レンジで温め、お皿に移して寿司の素を入れ切る様に混ぜます。
2 カップにたまご、砂糖、みりん、しょうゆ、塩を入れて良く混ぜます。
3 お鍋を熱したところに2を入れて、4本の割り箸を持ちすばやくぽろぽろになるまで混ぜます。出来た物は別皿に移しておきます。
すぐに火が通るので半熟の状態でまとめて余熱で仕上げるといいです。
4 お鍋をよく洗い、熱したら、みりん、お砂糖、ひき肉の順に入れ、最後にしょうゆを入れ水気が飛ぶまで更に炒めます。
5 絹さやを洗い、スジを取ったら、塩を入れたお湯で軽く茹でます。
6 冷水に取り、冷めたら千切りにします。
7 かにかまぼこは食べ易い大きさに切ります。
8 コップに酢飯、そぼろ、絹さや、酢飯、かまぼこ、炒りたまごの順番で詰め、最後にプチトマトを乗せて完成です。
栄養コラム
豚肉
今回そぼろに使用した豚肉についてお話したいと思います。
豚肉にはビタミン、ミネラルが豊富に含まれており、ビタミンB1は体を冷やす効果と疲労回復効果があるので夏バテ防止に最適な食材としても有名です。
他にもビタミンB2は美肌効果に、ビタミンB6は筋肉や血液の生成を助けたりします。
また、骨密度を高めるカリウム、血液に欠かせない鉄分が含まれているので、体内で生成できない分補える優秀な食材です。
よくダイエットしていたりするときにお肉を食べると太ると良く言いますが、それは食べ方によるもので、きちんと食材の味を活かした調理法で適量を食べれば問題有りません。
ダイエット中でも美味しく食べて欲しい食材ですね!
お食事コラム
ちらし寿司
ちらし寿司が生まれたのはその昔、備前(現在の岡山県)で大洪水がありました。
当時の藩主池田光政公が復旧の際に出したものが「一汁一菜令」です。
その名の通り、汁物1品、副菜1品以外は禁止という内容です。
食料不足に陥ったために出した条例とはいえ、村人達もこれには大いに困りました。
何とかして、主菜を食べたい!そこで魚や野菜をご飯に混ぜれば問題ないのではないかという考えが生まれました。
どうしても主食と主菜を食べたいという庶民が考えに考えた知恵ですね。
しかし、ひな祭りにちらし寿司を食べる風習はもっと前よりあったのです。
更に遡り時は平安時代。実はこの時からひな祭りという風習が始まったとされています。
当時はなれずしと言って色鮮やかではない海老と菜の花を具として、作ったとてもシンプルなお寿司が振舞われていたそうです。
ちらし寿司は平安時代にも別の名前であったという事は驚きですね!
こうして時代の変化とともに、見た目がキレイで、具沢山な今のちらし寿司が出来あがり、
いつしかひな祭りの日にはちらし寿司を食べるという習慣がついたという事です。
ちなみにちらし寿司は、散らし寿司だと縁起が悪いということで必ずひらがなでちらし寿司というように書きます。
お知らせ
ひな祭りを応援しています!ということでフロント前にて小さなひな祭りを開催しています。
到着した際に記念に1枚撮っていただき、旅の思い出にしていただければ嬉しく存じます。
編集後記
ひなまつりは女の子に悪いことが起きないように厄払いとしての役割があるそうです。私も御利益にあやかりたい!
日本には四季があります。また、季節ごとに行事や記念日があります。
そのときに出される食事を行事食といいます。日本ならではですね。
行事食は主に病院や学校、保育園で良く見かけます。
食育の一環として、また入院している患者様にもっと美味しくご飯を食べて頂きたいという栄養士さん、調理師さんの思いがあります。
食を通して記念日を思い出して日本の良き伝統を受け継いでいければということもあります。
もし身近で行事食に出会うことがあったら興味を持っていただけると嬉しいです。
次回は...う~んどうしよう。とまた悩みながらも掲載できるようにがんばります!
C.S